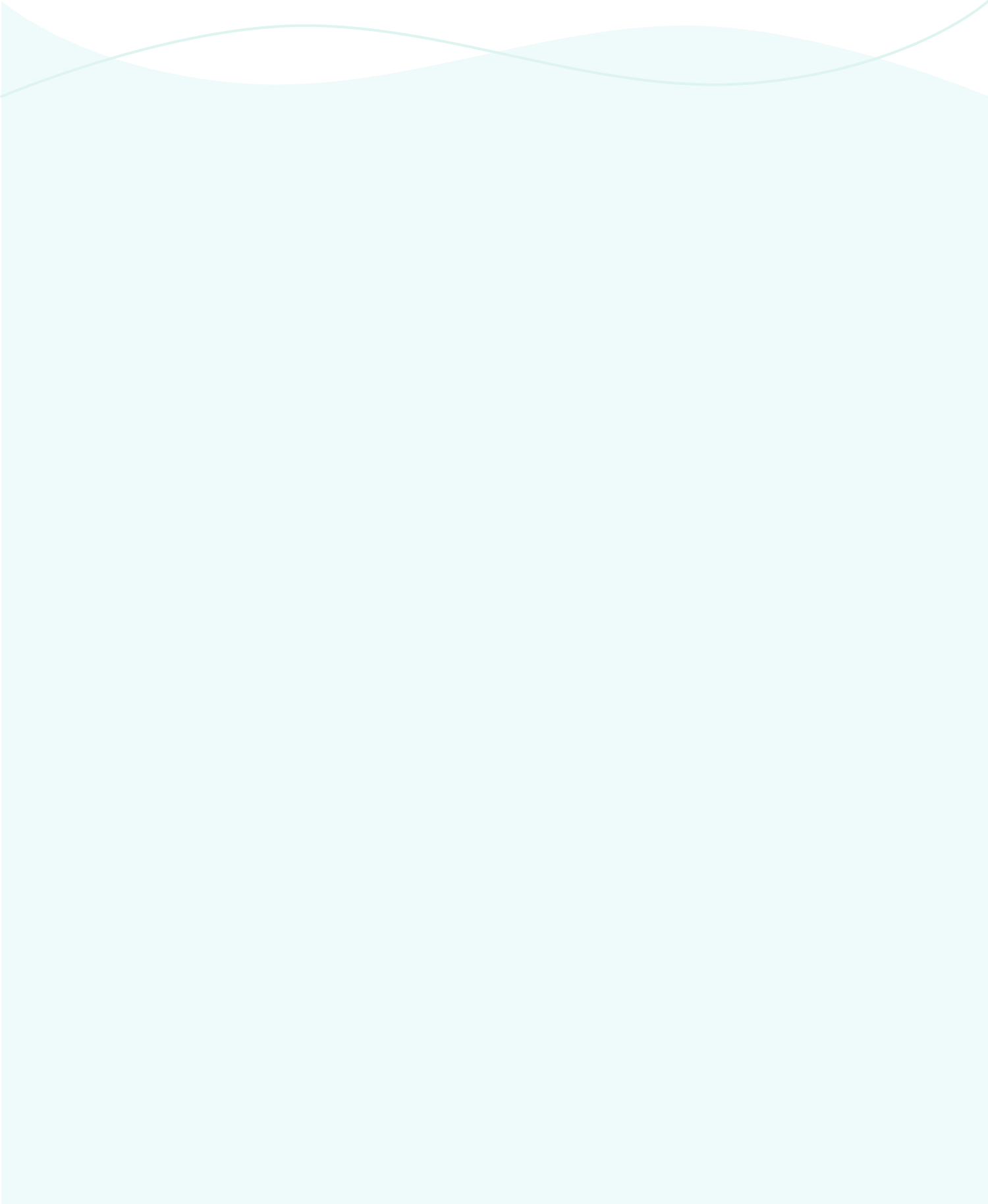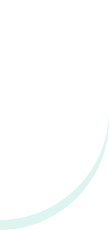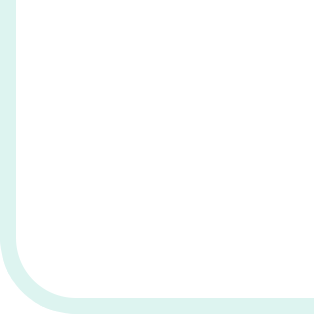ふるさとの味! 桃の節句のお菓子には「すわま」を!

古くから、湖西市新居町地区では、桃の節句お雛様飾りのお菓子として菱餅ではなく「すわま」が供えられます。この地方に伝わる伝統のお菓子「すわま」とは‥‥?
湖西市新居町地区の名物「すわま」。米粉、黒糖、砂糖、醤油、食塩などを混ぜて作られた昔ながらの素朴な餅菓子です。桃の節句ひな祭りの季節には菱餅の代用として供えられるなど、ふるさとの味として親しまれてきました。「すわま」は地域の歴史を伝える伝統のお菓子として文化庁が認定する「100年フード」に選定されました。
「すわま」の起源…… 東か西か?
この「すわま」は、作り方などから江戸時代に関東(江戸)で生まれた和菓子「すあま」が起源ではないかとされています。いつごろ当地に伝わったのかは定かではありませんが、おそらく当時の東海道を通って新居宿に伝わったといわれ、明治時代以降には一般家庭でも作られてきました。起源とされる「すあま」は、紅白のかまぼこ型や鶴の子餅と言われる卵型のものなどがあります。ほのかに甘いこの菓子は、関東地方では縁起物として寿甘(すあま)と表記されることもあり、七五三や誕生祝い、結婚式などの祝い事で使われています。
また、関西には「すはま(洲浜)」と言われる和菓子があります。「すあま」とは違い、きな粉などの豆粉を使った練り菓子です。とくに京都の老舗で作られてきた「すはま」は、断面の形状が波型に見え、家紋の州浜紋や波が寄せる砂浜の「州浜」から名付けられたと言われています。湖西市の「すわま」の特徴は、大きめの小判型で、表面には2本のみぞが入り波型に見えることです。一説には、小判形の生地に箸を押し付けて作るこの特徴ある波形が「州浜(すはま)」を表わしていて、それが転じて「すわま」になったとも言われています。
これらの言い伝えは、江戸と京を結ぶ東海道の中間点に近い新居宿ならではの、東西文化の交流を伝えるものと言えるのではないでしょうか。。
今も伝わる「すわま」の味
この「すわま」は、古くから一般家庭で作られ、家庭ごとに違った味があり、親から子へと継承されてきました。現在では家庭で作られることは少なくなりましたが、市内数店舗の菓子店やスーパーマーケットで販売されています。昔から家庭ごとの味があったように、現在でもお店ごとに違った味をお楽しみしいただけます。
桃の節句の季節、ぜひ「すわま」を味わってはいかがですか。
〇 新居宿「紀伊国屋旅籠資料館」では、毎年桃の節句の時期にあわせて、珍しい御殿飾りなどが並ぶ「ひなまつり展」を開催しています!!
「すわま」取り扱い店
※季節限定販売の場合もございます。

 |
 |